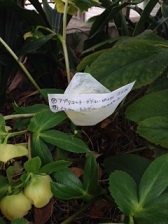梅雨を目前にして、
いま最も元気に咲き誇っているのはクレマチス・ピスタチオ。
たいした手入れもしないのに暗い庭をいつも明るくしてくれます。
そして先月の庭レポではまだ蕾だったハゴロモジャスミンは
今月初旬に満開になり、強い芳香が周囲の家にまで届いたようです。

山野草の西洋オダマキ・ピンクランタンは可憐に咲き、

三年前に小学校の課題で息子が育てたイチゴは
その後、地下茎で庭のあちこちに顔を出しては実をつけ、
(野趣溢れる味で決して美味しくはない(^^;)

暑さが大好きなニチニチソウは花をつけ始めました。

アジサイ・アナベルは梅雨が待ち遠しそう。

最後はクリスマスローズ。
昨年、交配にチャレンジしたものの
撒いた種から芽がでることはなく見事に失敗。
そしてこの春も懲りずに再チャレンジしました。

5月に採取した種を保存して秋に撒く方法で失敗したので
今回は採ってすぐに撒くやり方に変更。
今月から芽が出る来年の1月までたっぷり9か月間、
種が乾燥しないようにひたすら水やりです。
殺風景な鉢に水やりを続ける…私の根性が試されます。

7年目を迎えた我が家の庭。
この庭の居心地が悪かった植物は絶え、
居心地のいい植物や頑強な植物は育ち続けています。
庭も玄関周りも一通り植物で満たされたので
暫くは新しい苗は入手せず、今あるものを大切に育てていきたい。
地味で見映えのしない庭ですが、
季節の移ろいを感じさせてくれる大切な庭であります。