メリークリスマス!
夕方には、ケーキやご馳走を買う多くの人を見かけました。
おかげさまで、私は暖かい新居で家族揃って過ごしています。
家族揃って食卓を囲める、普通?のことが何より幸せなことですね。
皆さんは、どんなクリスマスをお過ごしですか?
さて、太陽と風で、できるだけ冷暖房を使わないことを
目標にした「パッシブハウス」。具体的にどうしたらいいのか?
設計士や工務店向けにかかれた本。
省エネ・エコ住宅設計究極マニュアル
断熱・気密・通風・採光・日射遮蔽・昼光利用・日射熱利用(パッシブソーラー)・ 設備計画(換気・暖房・冷房・照明・太陽熱給湯・太陽光発電)など、住宅を省エネルギー化する温熱環境の設計手法がイチから分かる! 「そもそも“エネルギー”とは?」といった基礎知識から、断熱や通風など設計に必要な要素技術の基本を解説。そのうえで、熱損失係数[Q値]や夏期日射取得係数[μ値]などの計算方法、設計の具体的方法を、実例を交えて紹介。低炭素時代の住宅設計に必携の1冊です!!
————————————
「省エネ・エコ住宅設計究極マニュアル」の基本的な考え方
————————————
・省エネ・エコ住宅は計算で裏付けられる
・パッシブデザインは、日照・通風など立地条件による
・換気・暖冷房・給湯・照明など計様々な要素のバランスが大事
・建築でなく、住まい方が大事
上記をふまえて、私が重要と思ったことは、、
・効率的な組み合わせを考える上でどんな暖房にするか?
・昼間の日射を蓄熱するために、壁・床の素材をそうするか?
無垢材の床は憧れですが、蓄熱を考えた場合、
「松=パイン」に軍配が上がります。タイルも蓄熱力が高いです。
クロスよりも塗り壁の方が高いです。
ウチは1Fは無垢のパイン、壁は一部塗壁にしました。

 スラスラわかる断熱・気密のすべて
スラスラわかる断熱・気密のすべて
 最高の断熱・エコ住宅をつくる方法
最高の断熱・エコ住宅をつくる方法

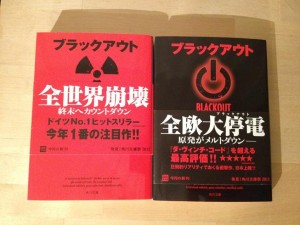
![チルチンびと 2010年 11月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51nciWsyD8L._SL160_.jpg)
 エコハウス私論
エコハウス私論